「どの転職エージェントを使えばいいのか?」
「転職エージェントは複数利用すべき?」
SEとして転職を考え始めたとき、このような点に悩む人も多いのではないでしょうか。
エージェントは数多く存在しますが、得意分野やサポート体制はそれぞれ異なります。合わないサービスを選んでしまうと「思ったように求人が紹介されない」「担当者との相性が合わない」といった不満につながることもあります。
逆に、自分に合ったエージェントを選び、複数をうまく活用すれば、理想のキャリアにぐっと近づくことができるでしょう。
この記事では、転職エージェントの選び方を紹介しつつ、複数利用のメリットやデメリットを解説します。効果的で、失敗しない転職活動をスタートしましょう。
転職エージェントを利用するメリットとは
SEの転職活動では、転職エージェントを活用することで効率的かつ有利に進められます。
●非公開求人にアクセスできる
エージェントを利用することで非公開求人にアクセスでき、幅広い選択肢から応募先を選べます。非公開求人には大手企業の求人や条件の良い求人も多く、希望にマッチする企業も見つかりやすくなります。
●応募書類の添削/面接対策をしてもらえる
また、履歴書や職務経歴書の添削、面接対策といったサポートも受けられるため、初めての転職でも安心です。
●企業との条件交渉をしてくれる
さらに、年収交渉や条件調整を代行してくれる点も大きなメリットです。面接終了後に、どんな印象だったか、条件面を含めた懸念点や相談事はないかなどの聞き込みやアンケート調査を行ってくれるエージェントもあります。それをもとに応募先企業へ交渉をしてくれるため、懸念点を解消しながら転職活動を進めることができます。
こうしたサポートを上手に活用することが、失敗しない転職の第一歩となります。
SEが転職エージェントを選ぶときの基準
SEとして転職活動を進める場合、転職エージェントは「どこを使うか」で大きく成果が変わります。特に初めての転職であれば、以下の3つを基準に選ぶのがおすすめです。
●IT・エンジニア領域に強いか
SEのキャリアは業界や技術ごとに専門知識が必要なため、ITやエンジニア職に特化したエージェントかどうかは重要です。専門性のあるエージェントなら、キャリアパスや技術スキルを理解した上でマッチ度の高い求人を紹介してくれます。
●求人の量・質
量があることで、希望の企業に出会える可能性が高まります。ただ、単に求人件数が多いだけでは意味がありません。自分の希望条件に合う質の高い求人がどれだけ揃っているかも重視しましょう。非公開求人や大手企業や優良な求人を多く持っているかが、重要なポイントになります。
●サポート体制
職務経歴書の添削や面接対策、企業への推薦文の作成など、サポート体制の充実しているエージェントを選びましょう。エージェントによってサポート内容は異なります。特にSEは経験やスキルの見せ方次第で選考結果が大きく変わるため、こうした支援が手厚いエージェントを選ぶと安心です。
これら3つの基準を意識して選ぶことで、「思ったような求人が見つからない」、「サポートが物足りない」といった後悔を減らすことができます。
複数利用のメリット・デメリット
転職エージェントは1社だけに絞る必要はなく、複数登録する人も少なくありません。しかし、複数利用にはメリットもあれば、デメリットも存在します。
ここでは複数のエージェントを利用することのメリットとデメリットをそれぞれ紹介します。
それぞれを理解した上で、効果的に使えるようにしましょう。
メリット
複数の転職エージェントに登録する最大のメリットは、下記の3つです。
●選択肢の幅が広がる
各エージェントや特に業界専門のエージェントでは、独自の非公開求人や得意とする業界があるため、1つのエージェントだけでは出会えない求人にアクセスできる可能性が高まります。結果として、希望条件により近い企業や、思いがけない好条件の求人に出会えるチャンスも広がります。
●アドバイザーのアドバイス/相性を比較できる
転職エージェントのアドバイザーは、経験に差があるうえに、自分との相性の良し悪しもあるため、当然合う・合わないが出てきます。複数のエージェントのアドバイザーと話すことで、自分に合ったサポートを見つけやすくなるのも大きなメリットです。同じ業界・同じ職種への志望動機や自己PRの伝え方でも、アドバイザーによってアドバイスの角度が異なるので、自分にとって納得感のある方法を選びやすくなります。
●各エージェントの得意分野を活かせる
各エージェントには得意とする業界や企業規模があります。複数社を組み合わせることで、IT特化型から大手総合型や若い企業まで、幅広い情報をカバーでき、偏りのない視点で転職活動を進めることができます。
デメリット
●ノルマ重視の求人案内をされることがある
転職エージェントのアドバイザーにはノルマがあります。そのため一部のアドバイザーは、自分の目標達成を優先して求人を紹介することがあります。結果として、自分の希望とかけ離れた案件を強く勧められたり、応募を急かされたりするケースも少なくありません。とくに転職活動に慣れていないと、アドバイザーからの提案を断りにくいと感じてしまい、結局ミスマッチな企業に応募して後悔する可能性もあります。自分の軸が決まっていなかったり、転職活動に慣れていないと、流されやすいという点はデメリットといえるでしょう。
●連絡や管理の手間が増える
複数のエージェントを併用すると、それぞれから求人や面談の案内が届くため、メールや電話の対応が煩雑になりがちです。また、希望条件を都度伝えたり、スケジュールを調整したりといった管理の手間が増えるのは避けられません。忙しい時期に重なると、対応するだけで一杯一杯になってしまうという状況にもなりやすいです。効率的に進めるには、自分の中で連絡の優先度を整理しておくことが必要です。
●対応に時間を取られることもある
アドバイザーとの面談ややり取りは、安心感を得られる一方で時間を取られる側面もあります。平日の夜や休日に面談が入ることも多く、仕事やプライベートとの両立が難しいと感じることもあるでしょう。複数のエージェントを利用すれば、その分だけ諸々の対応に時間がかかってしまうため、注意が必要です。
複数エージェントを上手に活用するポイント
複数のエージェントを活用するには、「どのエージェントを主軸にするか」「情報をどう整理するか」など、自分なりに工夫をしながら、必要な情報を見極めていく必要があります。
ここでは、どういったことを意識すればよいのか紹介します。
メインのエージェントを決める
複数のエージェントを使う場合、全てを同じ比重で利用すると混乱しやすくなります。求人紹介や面談のやり取りを効率的に進めるためには「メインで使うエージェント」を1社決めておくのがコツです。
仕事をしながら進める転職活動では、使える時間が限られています。主軸とするエージェントを決めることで、複数のエージェントの話に振り回されることがなくなります。
僕の場合、最初に面談したときの担当者との相性を基準に選びました。
必要な情報を整理する
複数登録をすると、それぞれのエージェントから求人紹介や連絡が届くため、情報がごちゃつきやすくなります。そこで役立つのが、自分が必要としている情報を整理することです。
最初のうちは、判断材料がないためたくさん届く求人を1つ1つ確認する必要があり、大変ですが、次第に求人を確認するスピードが早まります。そうなったタイミングで、どういったポイントを確認しているのかを意識するようにしましょう。
僕は実際に無意識のうちに確認している項目はどこなのか、意識するようにしました。
そうすることで、自分がどんな条件やポイントを重視しているのか把握でき、複数のエージェントから届く多くの求人も、取りこぼすことなく短時間で確認することができるようになりました。
比較する視点を持って活用する
同じ求人でも、エージェントによって募集条件が異なったり、選考時の条件交渉のスタンスが異なったりします。
僕も実際に同じ企業の求人でも「提示年収」「面接回数」「実際の業務内容」などに差があったことがあり、比較したからこそ気づけました。1社だけに頼ると見えない情報も、複数を照らし合わせることで判断の精度が高まります。
大切なのは「ただ多くの求人を見ていく」のではなく、自分にとって大事な軸(給与・働き方・環境など)を基準に比較していくことです。
まとめ|自分に合った選び方と併用方法を意識しよう
転職エージェントにはそれぞれ強みや特徴があり、どこを選ぶかによって得られる情報やサポート内容も変わってきます。
ただし、登録しすぎるとやり取りに追われてしまうため、自分が知りたい情報や比較基準を明確にした上で、メインで利用するエージェントを決めて効率的に活用していくことがポイントです。
転職と同様、転職エージェントとの相性もタイミングやご縁です。
複数エージェントの情報を取捨選択して、効果的に転職活動を進めましょう。

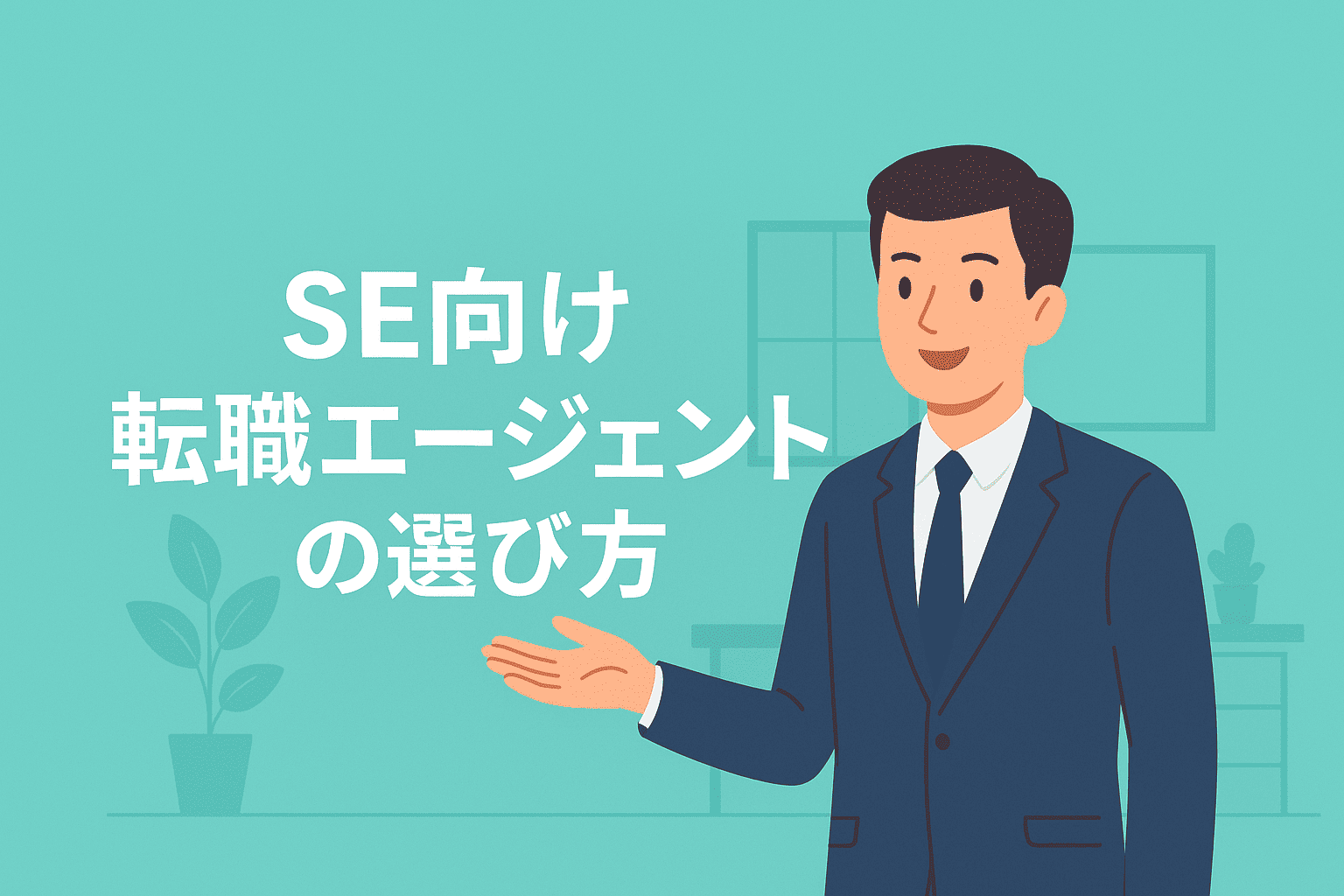
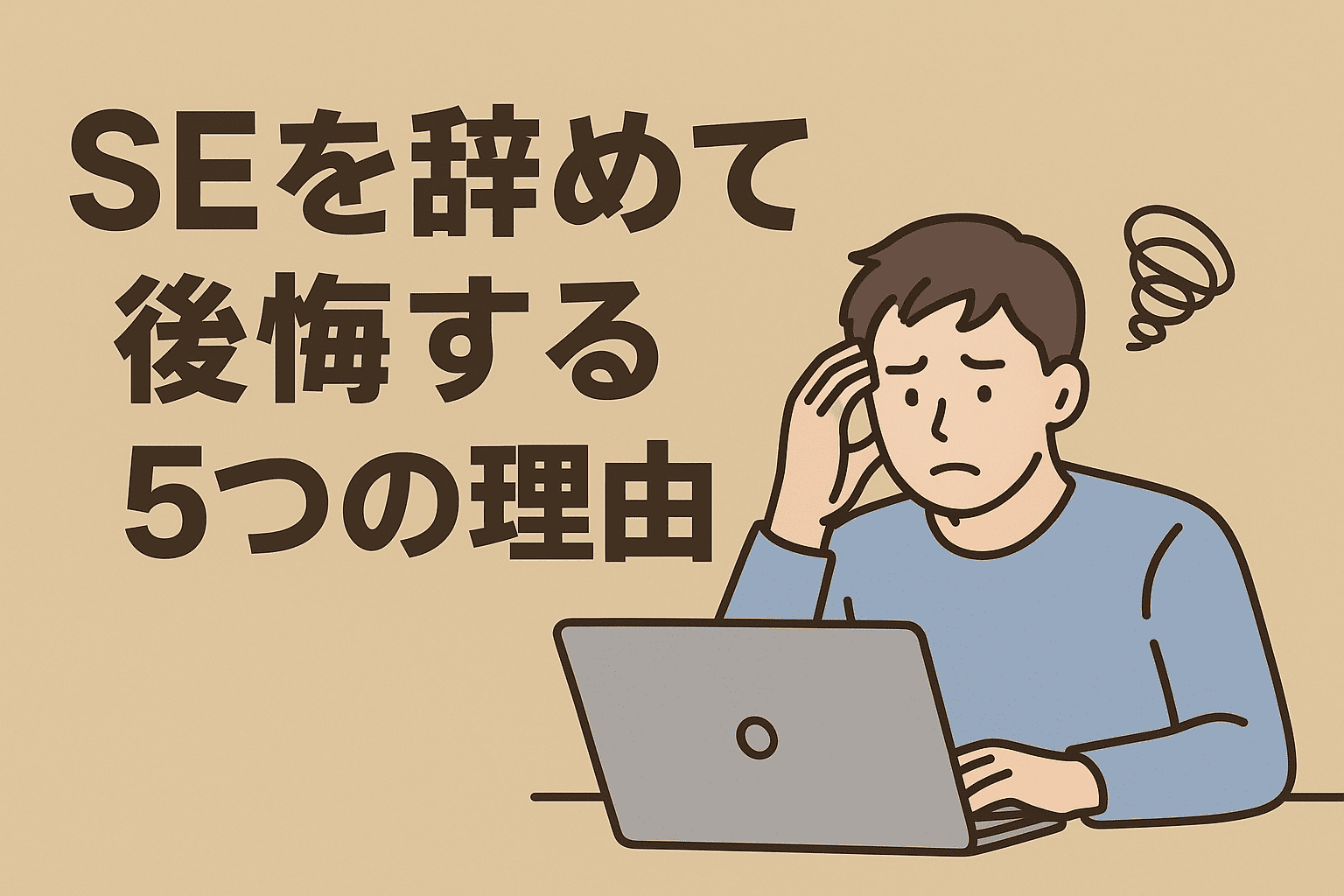
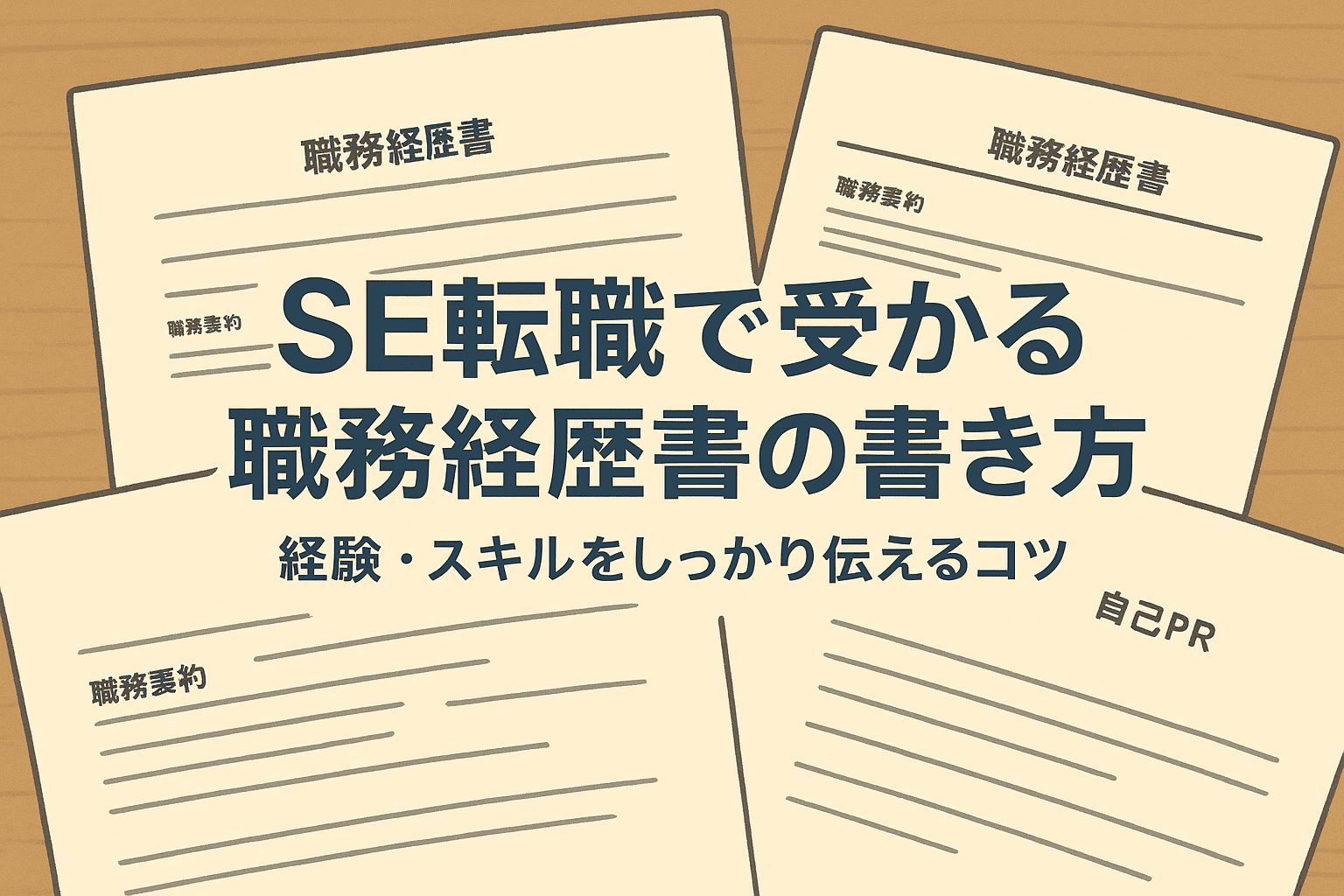
コメント